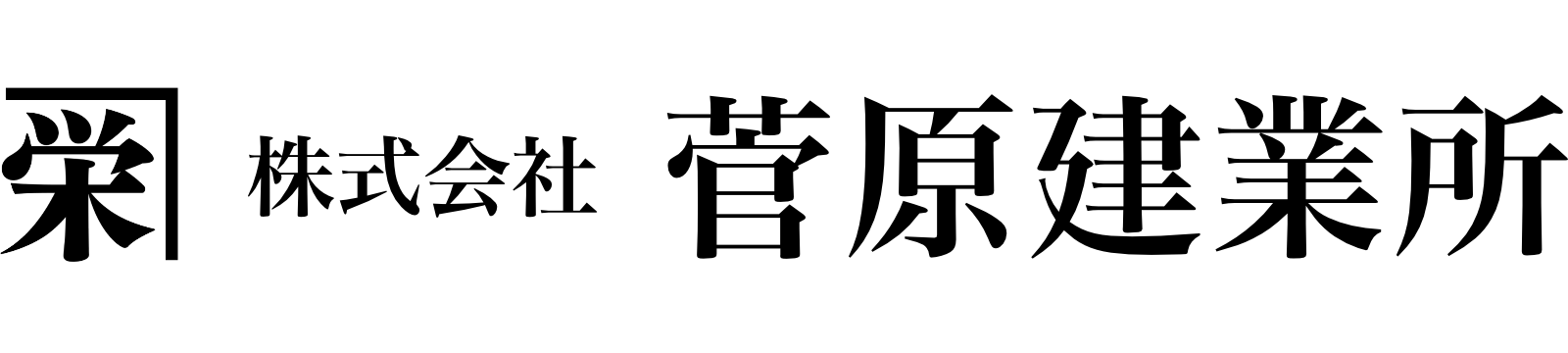
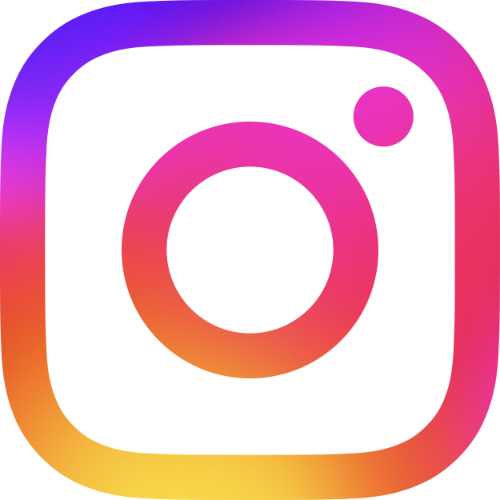

かつてシニア世代向けとされた平屋が、今や若い世代からも注目され「平屋ブーム」となっています。
この記事では、暮らしやすいというメリットだけでなく、知っておくべきデメリットも深掘り。
実際に建てる際の価格、土地選び、理想の間取りといった重要ポイントから、後悔しないための知識まで、二階建てとの比較を交えて多角的に解説します。
あなたにとって最適な住まい探しに役立つヒントを提供します。
記事のポイント

平屋とは、1階建ての住宅のことを指します。すべての居住スペースがワンフロアに収まっているため、階段がなく、水平方向への移動だけで生活が完結するのが最大の特徴です。かつては日本の伝統的な家屋に多く見られましたが、現代ではデザインや間取りが多様化し、新しい住まいの形として再評価されています。
この平屋の人気は、単なるイメージだけではありません。国土交通省の建築着工統計調査によると、居住用の木造住宅における平屋の着工棟数は年々増加傾向にあります。
例えば、2012年には約3万棟だったものが、2022年には5万7千棟を超えており、この10年で2倍近くも増えているのです。この数字からも、平屋を選ぶ人が着実に増えていることがわかります。
建築基準法上で明確に「平屋」という用語が定義されているわけではありませんが、一般的には「階数が1の建築物」として認識されています。ロフト(小屋裏収納)があっても、一定の条件(天井高1.4m以下など)を満たせば階数には含まれず、平屋として扱われます。
言ってしまえば、生活のすべてが一つの平面上でつながる住まい、それが平屋です。このシンプルさが、現代の多様なライフスタイルにマッチし、ブームの大きな要因となっています。

平屋がシニア世代だけでなく、子育て中のファミリーや若い夫婦からも支持されているのには、現代の価値観やライフスタイルの変化が大きく関係しています。主な人気の理由として、以下の3点が挙げられます。
現代は、モノを多く持たずに豊かに暮らす「ミニマリズム」という考え方が広まっています。平屋のコンパクトで無駄のない空間は、このようなシンプルな暮らしを求める価値観に非常にマッチします。また、家事動線が短く効率的であるため、共働きで忙しい世帯にとっても、家事の負担を軽減できるという実用的な魅力があります。掃除機を持って階段を上り下りする必要がない、洗濯物を1階で洗ってそのまま庭やテラスに干せるといった手軽さは、日々の時短につながるのです。
最近の平屋は、「おしゃれでデザイン性が高い」ことも人気の大きな理由です。2階の重さを支える必要がないため、柱や壁の少ない開放的な大空間を実現しやすくなります。屋根の形状をそのまま活かした勾配天井や、大きな窓を設けることで、明るく伸びやかなLDKを作ることも可能です。また、コの字型やL字型にして中庭を設けるなど、プライベートな屋外空間を楽しめる設計の自由度の高さも、個性を重視する若い世代に支持されています。
天井が高いと、実際の床面積以上に空間が広く感じられますよね。シーリングファンを付けたり、こだわりの照明を選んだりと、インテリアを楽しむ幅も広がります。
終身雇用が当たり前ではなくなり、ライフステージの変化に合わせて住み替えも視野に入れる時代になりました。平屋はバリアフリー設計にしやすいため、自分たちが年を重ねた時の暮らしまで見据えて選ぶ方が増えています。子どもが巣立った後も夫婦二人で快適に暮らせる住まいとして、将来的な安心感があるのです。このように、一過性のブームではなく、長期的な視点での合理的な判断が、平屋人気を後押ししていると言えるでしょう。
平屋での暮らしには、二階建てにはない多くのメリットが存在します。これらを理解することが、平屋という選択肢をより深く検討する上で重要になります。
第一に、生活動線や家事動線が非常に効率的な点が挙げられます。すべての部屋がワンフロアにあるため、階段を使った上下の移動が一切ありません。例えば、「洗濯機から洗濯物を取り出し、そのままウッドデッキに干し、乾いたら隣のファミリークローゼットにしまう」という一連の作業が水平移動だけで完結します。この負担の少なさは、日々の暮らしに時間のゆとりをもたらしてくれるでしょう。
次に、家族とのコミュニケーションが取りやすいことも大きなメリットです。リビングを中心に各部屋が配置される間取りが多いため、家族が自然と顔を合わせる機会が増えます。子どもが帰宅してすぐに自室にこもってしまうということが少なく、家族の気配を常に感じながら安心して過ごせる環境は、子育て世代にとって特に魅力的に映るでしょう。
構造的な観点からは、地震や台風に強いというメリットがあります。平屋は建物全体の高さが低く、重心も低いため、揺れに対して構造的に安定しています。2階部分の荷重がない分、建物の形状がシンプルになり、地震の力を受け流しやすいのです。災害の多い日本において、この耐震性の高さは大きな安心材料となります。
これらのメリットが複合的に作用することで、平屋は世代を問わず快適で安心な暮らしを提供してくれる住まいとなり得るのです。
多くの魅力がある平屋ですが、一方でいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に把握しておかなければ、建ててから後悔することになりかねません。ここでは、正直に平屋のデメリットをお伝えします。
まず、広い敷地が必要になるというケースもあります。二階建てと同じ延床面積を確保しようとすると、単純に考えて建物を建てる面積(建築面積)が約2倍必要です。そのため、都市部などの土地価格が高いエリアでは、土地の取得費用が大きな負担となる可能性があります。
また、建築費用に関しても、坪単価が割高になる傾向があります。これは、建物の面積に対して、工事費の中でも高額になりがちな基礎部分と屋根部分の面積が広くなるためです。同じ延床面積の二階建てと比較した場合、建築費の総額が高くなる場合もあります。
平屋は建物の高さが低いため、周囲に高い建物があると日当たりや風通しが悪くなることがあります。また、すべての部屋が1階にあるため、道路や隣家からの視線が気になりやすく、プライバシーの確保に工夫が求められます。塀や植栽で目隠しをしたり、窓の位置を高くしたりといった対策が必要です。
防犯面での懸念もデメリットの一つです。すべての部屋が地面に近いため、侵入経路が多くなりがちです。そのため、防犯ガラスやセンサーライト、防犯カメラの設置など、二階建て以上にしっかりとした防犯対策が重要になります。
さらに、万が一の水害時には大きなリスクを伴います。洪水などで浸水した場合、二階建てなら上の階へ垂直避難が可能ですが、平屋では逃げ場がありません。家財すべてが被害に遭う可能性もあるため、ハザードマップを必ず確認し、浸水リスクの低い土地を選ぶことが絶対条件と言えるでしょう。

平屋を検討する上で、最も一般的な選択肢である二階建て住宅との違いを明確に理解しておくことが大切です。それぞれの特徴を比較することで、ご自身のライフスタイルや価値観にどちらが合っているのかが見えてきます。
ここでは、主な比較ポイントを表にまとめました。
| 比較ポイント | 平屋 | 二階建て |
|---|---|---|
| 土地効率 | 広い敷地が必要。建ぺい率の低い土地には不向きな場合がある。 | 狭い敷地でも延床面積を確保しやすい。都市部に向いている。 |
| 建築コスト | 基礎と屋根の面積が広く、坪単価は割高になる傾向。 | 坪単価は比較的安価。ただし階段や廊下のスペースが必要。 |
| 生活動線 | ワンフロアで完結し、効率的。階段の上下移動がない。 | 上下移動が発生し、家事動線が長くなりがち。 |
| バリアフリー性 | 非常に高い。老後も安心して暮らせる。 | 階段が障壁に。1階だけで生活が完結する間取りが必要になる場合も。 |
| 耐震性 | 高さが低く構造が安定しているため、一般的に有利。 | 構造計算が複雑になるが、現在の基準を満たせば安全性は確保される。 |
| プライバシー | 外部からの視線に配慮が必要。家族間のプライバシー確保も工夫が要る。 | 1階と2階で空間を分けやすく、プライバシーを確保しやすい。 |
| メンテナンス費用 | 外壁塗装などで足場代を抑えられるため、長期的に見て有利な場合が多い。 | 大掛かりな足場が必要となり、費用が高くなる傾向がある。 |
このように見ると、土地の条件や予算、そして「どのような暮らしをしたいか」という根本的な部分を家族で話し合うことが、最適な選択につながります。
例えば、広い土地が確保できる郊外で、自然とのつながりや家族の一体感を重視するなら平屋が向いているかもしれません。一方で、通勤・通学の利便性を優先して都市部に住みたい、あるいは家族それぞれのプライベートな時間を大切にしたいという場合は、二階建ての方が適していると言えるでしょう。

平屋を検討する際に、最も気になるのが「価格」ではないでしょうか。ここでは、価格の仕組みと費用について詳しく解説します。
平屋は二階建てと同じ延床面積で比較した場合、坪単価が1〜2割ほど高くなる傾向があります。この主な理由は、建物の価格に大きく影響する「基礎工事」と「屋根工事」の面積が、二階建ての約2倍になるためです。例えば、延床面積30坪の家を建てる場合を考えてみましょう。
このように、工事面積が広くなる分、材料費や人件費が増え、結果として坪単価が上昇するのです。
坪単価はあくまで目安です。ハウスメーカーによって算出方法が異なり、本体工事費のみで計算されることが多いため、別途付帯工事費(外構、地盤改良など)や諸経費(登記費用、ローン手数料など)がかかります。総額でいくらかかるのかを必ず確認することが重要です。
一方で、平屋は二階建てに必要な階段や、2階の廊下といったスペースが不要です。そのため、同じ部屋数や機能を持たせる場合、二階建てよりもコンパクトな延床面積で済むケースも多く、結果として建築費の総額が二階建てより安くなる可能性も十分にあります。
さらに、長期的な視点で見ると、平屋はメンテナンスコストを抑えやすいというメリットもあります。特に、10〜15年周期で行う外壁や屋根のメンテナンスでは、二階建てのような大掛かりな足場を組む必要がないため、1回の工事で数十万円単位の費用を節約できることも珍しくありません。
つまり、初期費用(建築費)だけでなく、住み始めてからかかる費用(ランニングコストやメンテナンスコスト)まで含めたトータルコストで比較検討する視点が、賢い家づくりには欠かせません。

理想の平屋を建てるためには、建物そのものだけでなく、土地選びが成功の半分以上を占めると言っても過言ではありません。平屋は二階建て以上に土地の形状や周辺環境の影響を受けるため、慎重な検討が必要です。
最も重要なポイントは、十分な広さと建ぺい率です。建ぺい率とは、「敷地面積に対する建築面積の割合」のことで、用途地域によって上限が定められています。例えば、100坪の土地で建ぺい率が50%の場合、建築面積は50坪までとなります。自分たちが希望する間取りや部屋数から必要な延床面積を算出し、それが収まる広さと建ぺい率の土地を探す必要があります。
次に、日当たりと風通しを左右する周辺環境の確認も欠かせません。平屋は高さがないため、隣に二階建てやマンションが建っていると、日当たりが大きく遮られてしまう可能性があります。購入を検討している土地には、時間帯や曜日、季節を変えて何度も足を運び、日差しの入り方や周辺の状況を確認することをおすすめします。
そして、デメリットの部分でも触れましたが、防災面の確認は必須です。特に水害のリスクについては、各自治体が公開しているハザードマップで浸水想定区域に入っていないかを必ず確認してください。地盤の強さも重要で、軟弱地盤の場合は地盤改良工事が必要となり、予算を圧迫する要因になります。
土地探しと並行してハウスメーカーや工務店に相談し、専門家の視点から土地を評価してもらうと、より安心して決断できるでしょう。
平屋の魅力を最大限に引き出し、快適な暮らしを実現するためには、間取りにいくつかの工夫を凝らすことが重要です。ワンフロアという特性を理解し、デメリットを解消するような設計を心がけましょう。
課題となりやすい採光と通風の確保については、建物の形状を工夫するのが効果的です。敷地に余裕があれば、建物をL字型やコの字型に配置し、中央に中庭(パティオ)を設けるプランがおすすめです。中庭に面して大きな窓を設置することで、家の中心部まで光と風を取り込むことができます。中庭はプライベートな屋外空間として、子どもの遊び場やバーベキュースペースとしても活用できます。
敷地の制約で中庭が難しい場合は、屋根に天窓(トップライト)や、壁の高い位置に高窓(ハイサイドライト)を設置する方法も有効です。これらは周囲の視線を気にすることなく、安定した光を室内に届けてくれます。
次に、収納スペースの確保も平屋の間取りにおける大きな課題です。二階建てのように階で収納を分けることができないため、計画的に配置する必要があります。平屋の利点である屋根裏空間を活かしたロフトや小屋裏収納は、季節物や使用頻度の低いものをしまうのに最適です。また、廊下を極力減らし、その分ウォークインクローゼットやパントリーなどの集中収納を設けると、家全体がすっきりと片付きます。
家族間のプライバシーに配慮したゾーニングも大切です。家族が集まるLDKなどの「パブリックスペース」と、寝室や書斎などの「プライベートスペース」を意図的に離して配置したり、廊下や収納を間に挟んだりすることで、生活音を気にせず静かに過ごせる空間を確保しやすくなります。お客様が来た際にも、プライベートな部分を見られずに済むというメリットもあります。
平屋ブームに乗り、憧れだけで家づくりを進めてしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔につながる可能性があります。ここでは、先輩たちの失敗談から学ぶ、後悔しないための具体的な注意点を解説します。
最も多い後悔の一つが防犯面での不安です。すべての部屋が1階にあるということは、どの窓も侵入経路になり得るということです。「夜、窓を開けて寝るのが怖い」「留守中が心配」といった声は少なくありません。対策としては、侵入に時間のかかる防犯ガラスや二重ロックのサッシを採用する、人の動きを感知して点灯するセンサーライトや防犯カメラを設置するといった物理的な対策が有効です。また、家の周りに音の出る防犯砂利を敷くのも手軽にできる対策の一つです。
生活音の問題も、実際に住んでみてから気づくことが多いポイントです。ワンフロアで空間がつながっているため、リビングのテレビの音や話し声が寝室まで響いてしまい、家族の生活リズムが違う場合にストレスを感じることがあります。前述の通り、間取りを計画する段階でパブリックスペースとプライベートスペースをしっかり分ける「ゾーニング」を意識することが非常に重要になります。
また、収納量の不足も後悔につながりがちです。「最初は十分だと思ったけれど、子どもの成長とともにモノが増えて収まりきらなくなった」というケースです。現在の持ち物だけでなく、将来的な家族構成の変化やライフスタイルの変化を見越して、少し余裕のある収納計画を立てることが大切です。小屋裏収納や壁面収納など、空間を有効活用する工夫を取り入れましょう。
| 後悔ポイント | 対策 |
|---|---|
| 部屋が暑い・寒い | 断熱性・気密性の高い住宅性能を確保する。窓の性能にもこだわる。 |
| コンセントが足りない | 家具の配置を想定し、生活動線に合わせて多めに計画する。 |
| 外からの視線が気になる | 外構計画(塀、植栽)とセットで窓の配置を考える。目隠しフェンスなども活用。 |
これらの注意点を一つひとつクリアにしていくことが、満足度の高い平屋づくりへの近道となります。
【国土交通省】住生活基本計画(全国計画)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000032.html
【国土交通省】障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブック
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000049.html
【WIKIBOOKS】建築基準法第28条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC28%E6%9D%A1
【政府広報オンライン】住まいの防犯対策
【全国防犯協会連合会】防犯性能の高い建物部品目録
【国土交通省】不動産情報ライブラリ
はい、栗原・大崎エリアでも、若い世代からシニア層まで幅広い方に平屋が注目されています。ワンフロアで生活が完結するため家事動線がスムーズで、家族のコミュニケーションも自然と増えるのが大きな魅力です。また、構造的に地震の揺れに強く、将来のメンテナンス費用を抑えやすい点も選ばれる理由です。
平屋は基礎や屋根の面積が広くなるため、同じ延床面積の二階建てと比べると坪単価が割高になる傾向があります。しかし、階段や廊下のスペースが不要なため、コンパクトな設計でも効率的な間取りが実現できます。
総額では二階建てと大きく変わらないケースも多いので、まずはご相談ください。
平屋はワンフロアに全ての部屋を配置するため、一般的に二階建てよりも広い敷地面積が必要になります。登米市や一関市周辺は比較的広い土地を確保しやすいですが、ご希望の間取りや駐車スペースによって必要な広さは変わります。
弊社では土地探しからご要望に合わせた最適なプランをご提案します。
確かに平屋は地面に近いため、二階建てに比べて侵入経路が多くなる可能性があります。そのため、窓を防犯ガラスにしたり、人感センサー付きの照明を設置したりといった対策が有効です。また、設計段階で道路からの視線を遮るような間取りや、庭に目隠しフェンスを設けるなどの工夫も重要です。
平屋は家の中心部まで光が届きにくいという懸念がありますね。しかし、建物の形をL字型やコの字型にして採光面を増やしたり、中庭(パティオ)を設けたりすることで、家の隅々まで自然光を取り込むことができます。
土地の形状や周辺環境に合わせて、明るく開放的な平屋をご提案します。
ご家族4人ですと、3LDK~4LDKの間取りで、延床面積30坪前後が一つの目安となります。平屋は廊下などのデッドスペースを減らしやすいので、同じ30坪でも二階建てより広く感じられることが多いです。
お子様の成長や将来のライフプランに合わせて、最適な広さと間取りを一緒に考えましょう。
よく聞かれるのは「収納をもう少し作れば良かった」という点です。平屋は小屋裏(屋根裏)スペースを収納として活用しやすいので、設計段階で計画しておくことをお勧めします。また、生活動線を意識しないと部屋の移動が意外と多くなることも。
弊社では家事や生活が楽になる動線を第一に考えて設計します。
平屋はすべての居住スペースが1階にあるため、万が一の浸水リスクには特に注意が必要です。大崎市が公開しているハザードマップなどを必ず確認し、土地の安全性を確かめることが重要です。
基礎を通常より高くするなどの対策も有効ですので、土地選びの段階からお気軽にご相談ください。
平屋は階段がないため、それ自体が非常にバリアフリー性能の高い住まいです。さらに、室内の段差をすべてなくし、廊下やトイレの幅を広く設計することで、車椅子での移動もスムーズになります。
玄関のスロープ設置や、浴室・トイレへの手すり取り付けなど、細やかな配慮で長く安心して暮らせる家をご提案します。
シンプルでモダンな箱型のデザインから、屋根の形を活かしたナチュラルなカフェ風、あるいは重厚感のある和風モダンまで、平屋は多彩なデザインを実現できます。内装も、勾配天井にして梁を見せることで、開放的でダイナミックな空間を演出できます。
お客様の理想のイメージをお聞かせください。
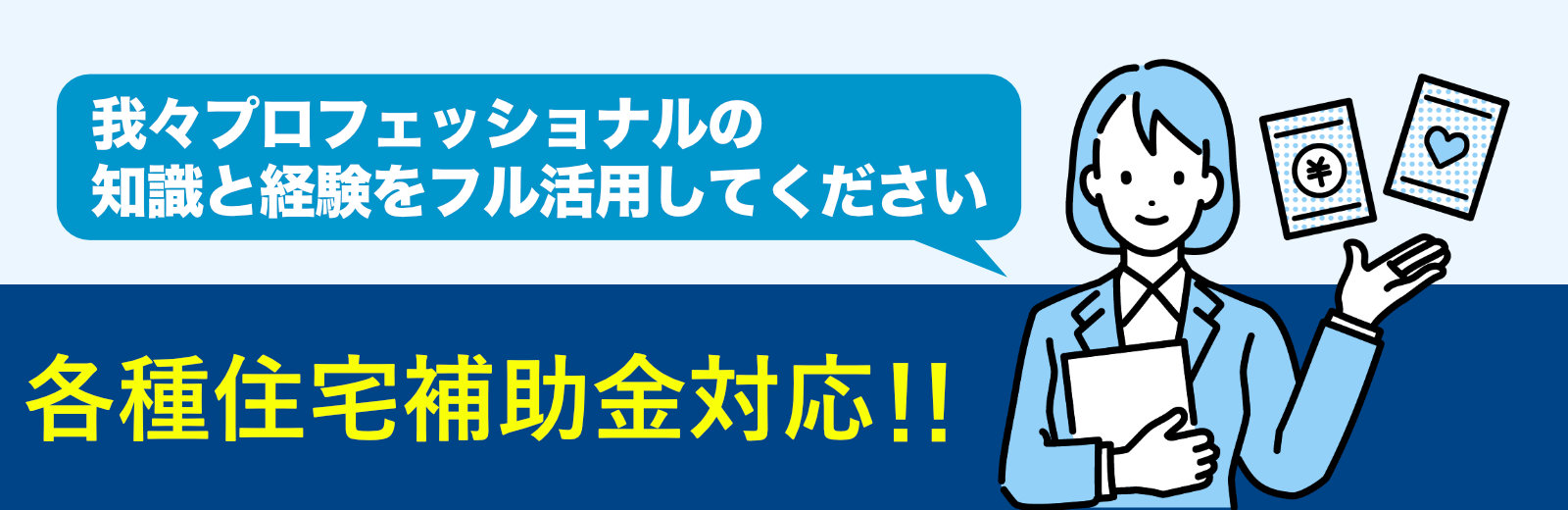
\ 各種住宅補助金対応!!夢のマイホームが “グッと” 身近に /
\ 夢のマイホームが “グッと” 身近に /
【住宅補助金】は注文住宅やリフォームにかかる費用の一部を補助。経済的な負担を軽減することができます。
菅原建業所がイチからしっかりサポートいたします!
| 床面積 | 110.75㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 337.23㎡ |
| 工法 | 木造・2階建て・在来軸組工法 |
| 所在地 | 宮城県登米市 |
| 竣工年 | 2024年 |
| 仕様・性能値等 | 認定長期優良住宅 耐震等級3 換気システム:第一種ダクトレス全熱交換換気 UA値:0.48W/㎡k C値:0.6㎠/㎡ |
| 取得補助金計 | 206万円 |
| 補助金申請事業 | 令和5年度地域型グリーン化事業 県産材利用サステナブル住宅普及促進事業補助金 登米市魅せる登米材活用促進事業補助金 登米市住まいサポート事業補助金 |



\ 補助金を利用して建築した注文住宅 /
【緑に囲まれた登米の家】
\ 補助金を利用した注文住宅 /
「緑に囲まれた登米の家」
菅原建業所では、あらゆる建物のこと、小さなことから大きなことまで何でもご相談ください。
もちろんご相談は無料です!長年の経験とノウハウを持った建築のプロが親身にお答えいたします。